2025年10月6日

『めぐみ薬局』は、1999年にぽぷらグループの保険調剤薬局としてスタートしました。地域にお住いの高齢者や障がい者、子供等、幅広い世代を、より身近な存在でご支援したいとの思いで設立しました。地域の困りごとに応えるため、利用者アンケートに取り組み、 アンケートを通じて、『こんなサービスがあれば良いのに』 といった声を一つひとつ形にし、健康⾷品・サプリメント等の販売、補聴器販売取次、OTC薬の販売等のサービスを増やし、2025年に高齢者等終身サポート事業を始めました。
家族のように最後まで面倒を見てほしい
事業を始めるきっかけは、地域住民の『入院しても、施設入所が必要になっても、どんなことが起こっても、家族のように最後まで面倒を見てほしい』という声。その言葉の裏には、『緊急時に頼れる人がいない。入院したらどうしよう』、『家族に負担をかけたくない』、『葬儀やお墓の手続きを頼める人がいない』といった今後の生活に対する不安。この課題をサポートしているのが、介護保険制度の中心的存在であるケアマネジャー。身寄りのない方、親族が遠方に住んでいる方等が入院した時、入院手続き等、本来家族が行っていることをケアマネジャーが行っています。ただケアマネジャーはサービス調整が職務であり、入院手続きや緊急時の対応等は本来の役割ではありません。本来の役割+シャドウワークを行わざるを得ない現実があり、ケアマネジャー自身疲弊し、本来担うべき役割が滞り、支援すべき方々の対応が遅れるという弊害が出ています。高齢者がより安心して生活できる支援、ケアマネジャーが本来の役割に専念できる支援を行いたいと考え事業を開始しました。

ガイドラインが示された
「高齢者等終身サポート事業」の実際
高齢者等終身サポート事業は、一人暮らしの高齢者の方や、ご家族が遠くにお住まいの高齢者の方などで、医療機関への入院・介護施設等への入居の際に必要となる身元保証人(身元引受人)を頼めない、又は親族はいるが頼りたくない方をご支援するサービスです。
具体的なサービスの内容は、身元保証サービス、死後事務委任、日常生活支援です。
身元保証サービスは、医療機関への入院や施設入居時の身元保証や緊急時の対応等を行います。具体的には、入院・施設入居の身元保証、入院・入居時の手続き、退院・退居時の物品整理・残置物処分、緊急時の対応等です。
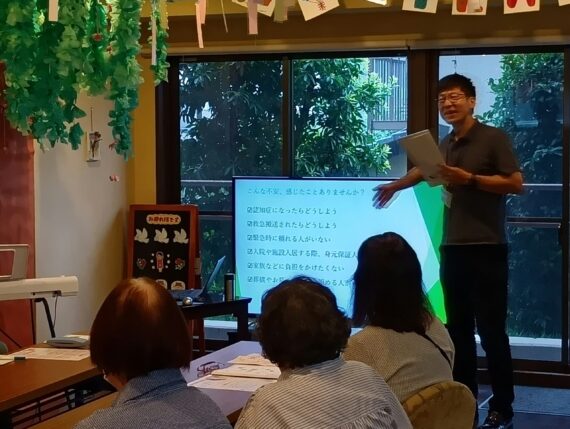
死後事務委任は、お亡くなりになられた際、葬儀手配や遺品整理、役所への届け出等の事務手続きを代行します。具体的には、死亡時の事務手続き、遺品整理、葬儀やお墓の手配、家族などへの連絡を行うサービスです。
日常生活支援サービスは、買い物等の外出の付き添いや大掃除、引っ越しの支援等を行います。
実際に事業を開始すると、様々な相談を受けます。例えば、身元保証や死後事務をサポートしてくれることになり今後の事が安心できるようになったので、死後の備えとして掛けていた生命保険の解約手続きをしてほしい。毎年、市役所で行っている税関係の手続きをサポートしてほしい。銀行の通帳が多いので、ある程度集約できるようにサポートしてほしい。自分が希望している納骨先を見たいので、連れて行ってほしい等の相談を受け、1つ1つご意向に沿って、ご支援させて頂いております。
相談者も相談内容も多岐
応えるために、専門性を備える
相談依頼は直接ご本人からの問い合わせや高齢者施設、ケアマネジャー、ボランティア等からの相談をきっかけに、ご支援させて頂いています。本人が相談できる、関係者が相談できる方は良いのですが、「将来に漠然とした不安はあるけれど、具体的に何が不安なのか…」という方もいらっしゃいます。そうした方の不安を少しでも整理し気持ちを改善し今後の備えにつながるように、地域に出向いて終活セミナーを開催しています。
本人だけでなく残される家族も万が一のことが起こった時に困らないように、また自分の望む医療や介護等が受けられるように、エンディングノートにご本人の意志を書き残すように働きかけています。

終活セミナーに参加される方は意識が高く、それぞれが明確な悩みを抱えておられます。セミナー終了後は個別相談を受けているのですが、相談内容は多岐にわたります。
面倒見てくれている姪に保険金が入るようにしているが、死亡後何日で保険金が支払われるのか?田舎にあった墓をしまい、こちらで新しく墓をこしらえたいが、田舎の墓は何もしなくて良いのか?施設に入るにはお金がいくら必要か?等、いろいろな相談を受けます。
自分の意思を明確にしておくために遺言書作成の相談を受けた際は弁護士と連携し、今のうちに不動産を処分し身軽になっておきたいと相談を受けた際は司法書士や不動産会社と連携し、その際の税金関係に関しては税理士と連携する等、窓口を一本化したうえで、様々な専門職と連携を図ることで、スムーズに困りごとを解決できるようにご支援しております。

専門職が本来の仕事に戻るための支援だが…
ケアマネジャーや施設長等の専門職が利用者を支援するうえで、利用者に何か起こった時に困らないように、高齢者等終身サポート事業を結び付けようと相談に来られるケースもあります。相談を受けると自宅訪問し、サービス説明するのですが、費用負担のことを考えて利用に二の足を踏む方がおられます。
「ケアマネジャーが支援してくれているので大丈夫です」、「必要性が差し迫るまで頑張ります」、「途中で払えなくなると困るので、逆算した結果、2年後にお世話になりたい」等、専門職からの相談案件は利用につながらないことが多いのが実情です。
ただ専門職、特にケアマネジャーは本来の業務ではない部分を担っていることが多いので、私たちのような事業者が領域外を担っていけるように、そして各専門職が本来の役割を担い、利用者や支援者の意識を変えていく必要があると感じています。
高齢者の「つつがない暮らし」を実現する
制度はできた。コストをどう捻出するか
一方、日々、相談対応を進めているなかで、大きな課題を感じています。それは経済的な理由で、利用したくても利用できない方の支援。
この仕組みは、専門職(特にケアマネジャー)の方に圧し掛かっている、本来業務以外の仕事を取り除くためでもあります。
ケアマネジャーは本来、介護や生活支援を必要とする高齢者等が様々な社会資源を活用しながら安心して安全に生活できるように、生活全般を調整するコーディネーター役。ですが、いろいろな場面でケアマネジャーがやらざるを得ない状況が増えています。
例えば、経済的な余裕がなく通院時にヘルパーを利用できない方は、ケアマネジャーが付き添い、経済的負担を軽減しています。急遽入院となったけれど家族が遠方ですぐ駆けつけられない場合、あるいは身寄りのない方の場合、家族の代わりに病院へ向かい入院手続き等を行わざるを得ない現実があります。

またご本人に支払い能力などの条件に問題はなくても、身元引受人がいないがために施設に入れない、病院に入院できない。そういったことが現実にあります。これは急変した時や病院での対応が困難になった時、病院でお亡くなりになった時に、対応してくれる家族等がいないと施設や病院は困るからです。こういった社会課題の解決策として、成年後見人という仕組みが既に存在しています。しかし地域の成年後見人は少なく、また申し立てをしても後見人が選任されるまでに3~6ヶ月程度かかります。申し立てには費用もかかり、その費用を誰が負担するのかといった課題もあります。
こうした様々な課題に対応するためにも、高齢者等終身サポート事業は、高齢者の生活支援において重要な役割を担うことになると思います。
経済的な理由で利用できない方もご支援させて頂けるように、今後、福祉基金を作り、寄付金を募ってご支援したいと考えています。この事業に共感して頂いた方が『寄付したい』と言ってくださるので、善意の心を困っている方への支援につなげ、より安心して生活できる循環型社会の構築につなげていきたいと考えています。

前田 稔氏
2026年1月16日
2025年12月19日
2025年12月3日